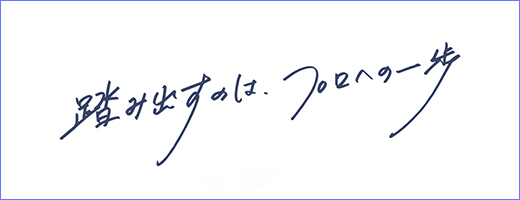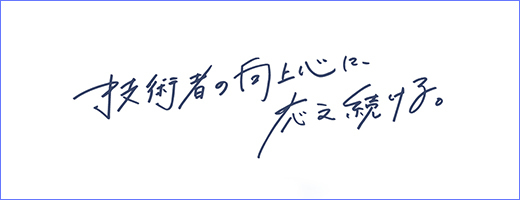Interview
生涯1社で送ったエンジニア人生。
オールジャパン体制の中で身に付いたマルチな能力。
機械系 生涯プロエンジニア(R)

エンジニア略歴
- 1984年メイテック入社
- 1984年~航空機・宇宙機器発射・管制設備機器の設計
- 1989年~航空機・宇宙機器発射・管制設備機器の設計
- 2024年3月定年到達
航空機への憧れが
技術の仕事につながる

育ったのは徳島県で、日用品が売っている店まで車で30分かかるような、のどかな場所でした。周りにあるのは山と川と田んぼだけ。野山を駆けまわり、釣りや探検ごっこをして過ごす少年時代でした。
そんな毎日の中で、はるか上空を飛ぶ航空機に憧れを持つようになりました。田舎で静かなので、どんなに高い空を旅客機が飛んでいても音で分かったのです。家から飛び出して空を見上げながら、「いつか航空機のパイロットになりたい」と思うようになりました。
やがて高校生になり、最初に目指したのは航空自衛隊のパイロット。そこから民間機のパイロットに目標を変えたのですが、先生に学力的に難しいと言われ、ならば航空の整備士になろうと航空関係の専門学校に入りました。ところが卒業のころは航空不況で、整備士の募集が全くない状態でした。
それでも航空機に関わりたいという思いは消えません。「整備ができないなら設計をやりたい」と考えてエンジニアを募集する雑誌を見てみました。そこで、ある航空機メーカーを取引先としている、当時の名古屋技術センターに出合いました。技術的なことは全く知らなかったのですが、だめもとで応募すると、運よく合格。入社して研修を経て、1カ月後には航空機メーカーに配属されたのです。
紆余曲折ありましたが、子どもの頃に空を見上げて抱いた、夢のスタートラインに立つことができました。
息の長い開発の中で
昼も夜も学んで食らいつく日々
配属先は、航空機そのものではありませんでしたが、航空機・宇宙機器の発射・管制設備機器の設計部署。4人程のチームで取り組む小さな案件の、立ち上げから携わりました。
仕事の内容は、元々海外メーカーが製造した機器を、日本で使えるようにローカライズして、後方支援すること。この機器は、点検や修理を重ねて数十年間現場で運用するような、息の長いものでした。運用や整備のためのマニュアル作成をはじめ、消耗部品を日本で調達するために、図面を描いて発注し、実際に使えるかのチェックを繰り返しました。
初めの頃は右も左も分からず、専門知識の少ない私は勉強に次ぐ勉強の日々。周りの人たちが当たり前に理解していることを、自分は昼間は知ったかぶりをして、夜に一生懸命調べてやっと追いつく……その繰り返しでした。
また、パソコンがない時代でしたので、上司が走り書きしたメモを私が清書して、資料の体裁に整えるような細々とした仕事がありました。中身を理解しなくては形にできないため、その都度調べて学び、どうしても分からないところは周囲に教えてもらいました。地道でしたが、自分の手で描くことで、理解しながら知識を頭に叩き込むことができました。
この機器のプロジェクトが立ち上げから5年ほどすると一段落して、次のプロジェクトに移ることに。そして35年たった今も携わり続けています。
大規模プロジェクトで培った
プロジェクトマネジメント力

この仕事は非常に大きな予算が動くプロジェクトで、私が配属されたお客さまだけでなく、ある意味「オールジャパン体制」で複数の日本の大メーカーが参加していました。その中で、機器ごとに幹事となるベンダーが選定されて、開発はその幹事社が中心となって、他のベンダーの開発状況を管理しながら進めます。
そして私が担当していた機器では、私たちが幹事社をやることになりました。どの部分をどのメーカーに依頼するかの差配から、機械や電気部分の構成の検討まで、あらゆることをしなければいけません。メイテックではME、EL、IT のようにエンジニアの専門が分類されていますが、そんなことを言っていられない、分野の垣根なくあらゆる知識が必要とされる環境でした。そして何より、プロジェクト全体をマネジメントし、交渉する能力が重要でした。
海外の機器を日本向けにローカライズする際にはこんな要望もありました。「日本で使うには駆動音が大きすぎるので、性能を変えずに音だけ小さくしてほしい」というものです。海外では問題ない音量でも、日本では問題視されてしまうというのです。
まずはどうすれば音を小さくできるかを考えます。ファンなどの部品を替えてみたり、全体的な設計のバランスを取り直したりして、調整を繰り返します。騒音に関する法律のセミナーにも通い、そもそもどのレベルまで下げる必要があるのかも学びながら進め、なんとか静音化を実現しました。
このような環境下、配属当初から実に20年ほどはがむしゃらに走り続ける日々でしたが、気がつけばお客さま先社員の高学歴なエンジニアと対等に仕事ができるようになっていました。製品のユーザーとお会いして名刺交換すると、問い合わせが私指名で直接入るなど、周囲の信頼を実感する機会が増え、非常にやりがいになりました。
厳しい面も多い仕事でしたが、チームで仕事をしていたので、プロジェクトが完了したときの達成感を皆で分かち合えたのもうれしいことでしたね。
古い機器に最新技術を
搭載する開発の醍醐味

私が担当した製品は、ライフサイクルが非常に長いものですが、ただ古い機器のメンテナンスをしているわけではありません。その中身は常に最新の技術を導入し、進化しています。見た目は30年間同じでも、中は完全な別物になっているというのも、面白いところです。
そのぶん、設計は非常に難しく、挑戦の連続でした。例えば、機器のライフサイクルの間に、搭載されているディスプレイがCRT から液晶パネルになったり、通信の規格がIP 化されたり、技術の変革が起きます。それらにどう対応させていくかを考えることは、エンジニアとしての成長機会であり、醍醐味でもあります。
最近の技術の傾向として、私が興味深いと思っていることがあります。それは、民生用機器に使われる素材、部品のクオリティが上がっていることです。タフなスマートフォンやパソコンなどで「MIL規格」という売り文句を聞いたことがあるかもしれませんが、民生品でも高いスペックを持つものが量産されるようになったことで、これらの部品を開発に活用したらコスト削減につながるのでは、と考えたりするのが面白いです。
また、最近流行の生成AI についても自身の業務での活用用途、あるいは新技術の導入よりも先に解決すべき課題はないのかを考えて、お客さまへ進言できるよう備えています。これからのエンジニアは、新しい技術の動向に今まで以上に注意を払い、それが本当に「使える」かを吟味する必要があると思います。
2024 年に定年を迎えますが、引き続き仕事を続けたいと思っています。実は、私の職場には70歳でも現役で働くメイテックエンジニアの大先輩がいまして、その人が1つの目標です。
他の多くのメイテックエンジニアと違って、私のエンジニア人生は1つの会社の同じ部署で過ごしてきたもの。メイテックの中ではユニークだとは思いますが、ここでしか得られない視座や技術も大いにあり、自分には合っていた、満足できるキャリアです。
(インタビュー:2023年12月9日)