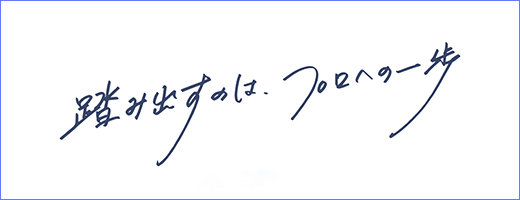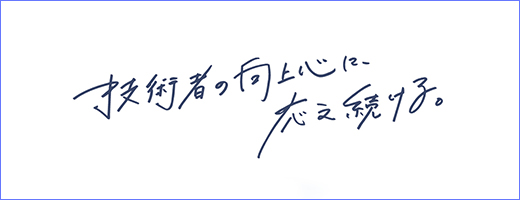Interview
トレンド言語と共に培った技術と人間力。
不器用な自分が続けられたソフトウェアの魅力。
IT系 生涯プロエンジニア(R)

エンジニア略歴
- 1986年メイテック入社
- 1986年~CAD図面入力・システム開発
- 1987年~原子炉破断事故シミュレーションシステムのカスタマイズ
- 1989年~ヘッドライトの配光シミュレーションシステム開発
- 1990年~CAD図面管理データベースおよびCADのカスタマイズ
- 1995年~ワイヤーハーネスのCAEシステム開発
- 1997年~パソコンのサウンドドライバー開発
- 1999年~ソースコードに対するプロジェクト管理システム
- 2000年~総合生産ライン移行に伴うツール開発
- 2000年~総合生産ライン拡張によるソフトカスタマイズ
- 2000年~電気・電子楽器の新モデル開発
- 2001年~電気・電子楽器(ミキサー類)の設定制御システム開発
- 2010年~電気・電子楽器向けEthernetAVBドライバー研究開発
- 2010年~電気・電子楽器の設定制御システム保守
- 2014年~三次元グラフィックシステムの開発
- 2014年~医療洗浄支援システムの開発
- 2015年~測定機器データ集計システムの開発
- 2015年~イメージスキャン処理のTWAIN化
- 2015年~測定機器データ集計システムの開発
- 2016年~生産管理システムの開発
- 2019年~ゴルフカートのナビシステム開発
- 2020年~ゴルフカートのIoTシステム先行開発
- 2022年~AIエッジ端末開発
- 2023年~ロボットアームのティーチングペンダント開発環境の要素技術検証
- 2024年3月定年到達
「スキルが身に付けばいい」
軽い気持ちでメイテック入社

私は子どもの頃、かなり内気でおとなしい性格でした。ものをつくることは好きで、ジオラマ模型をつくっていましたが、手先が器用ではなく、きれいにつくるのは苦手でした。どちらかというと理系の科目のほうが試験の点が良かったので、大学は理系で工業経営学科に入りました。卒論はコーヒーメーカーを分解して、余分な部品を外して商品力を高める研究(VE)をしました。これは面白かったのですが、この方面に進みたいという具体像が見えていたわけではありませんでした。
就職も、「ここに行きたい」という企業はなく、ゼミの教授に紹介された1つがメイテックで、技術が早く身に付く会社だと聞いて関心を持ちました。とりあえず自分の中で技術を磨いて、やりたい方向性が見えてきたらその方面に進めばいいという判断で試験を受け、メイテックに入社しました。
入社後はソフトウェアのエンジニアとして研修を受けていましたが、なかなか仕事が決まらず、少し焦ったのを覚えています。
ようやく配属が決まったのは、入社から11カ月たった頃でしたが、言語を1年近く学べたのは良かったですね。原発関連の企業で、私の担当は原子炉の冷却パイプの動作シミュレーションでした。原子炉自体は米国製で、日本の原発の構造とは全く違うため、配管の設計時には詳しいシミュレーションが必要でした。
当時のスーパーコンピューターにプログラムを読み込ませて、実行して答えを確認します。大学やメイテックの研修で学んでいたプログラム言語だったので、問題はありませんでした。プログラムを書けば正しい答えが出る仕事は、不器用な自分にも合っていると思いました。
新しい技術の勉強は
毎日の通勤電車の中で
このお客さまには部署は違うものの、電気系や機械系の同年代のメイテックのエンジニアが多く配属されていました。そのため、いろいろと教えてもらったり人間関係ができたりして、最初に働く場所としては良い環境だったと思います。
この頃、開発環境は大型コンピューターからワークステーションに変わりました。お客さまがCAD を使う際のメニュー画面のカスタマイズや、データベース管理の便利ツール的なものをつくったりもしました。CADは自分のやったことが絵として見え、手先の器用さは関係なく表現できることが分かり、長くエンジニアとして続けていくきっかけになったように感じます。
一方で、当時の私はまだ若く、お客さま先の現場の人と意見が違ったり、合理的ではないと思ったりしたら、衝突していました。上司にたしなめられることもあり、現場の事情も理解して、バランスの取れたコミュニケーションスキルを磨かなければいけないとだんだん気付いていきました。
3社目のお客さま先でワイヤーハーネスのCAEシステムを担当したとき、初めてプログラムのコーディングでなく、その上流工程の設計開発を担うことになりました。個々のプログラムを部品としてとらえ、1つのプログラムをつくる「オブジェクト指向」を用いた開発手法です。全く知らない考え方でしたが、なんとか食らいつきました。通勤が新幹線を使って往復4時間かかるほどの遠距離だったので、その時間を活用して勉強し、知識を身に付けました。
時代の変化に合わせて
新たな開発環境に対応

このお客さま先では、同業他社含めて、総勢200人超が参加する大きなプロジェクトに入り、新しい方法で開発を進め、成功したことは大きな自信につながりました。
しかし次のお客さまでの業務は、パソコンのサウンドドライバーの評価で、開発の仕事ではありませんでした。ちょうど開発環境がパソコン(Microsoft Windows)に移行したタイミングだったため、ここでおよそ2年半、開発から離れたことで、その後の開発者としての需要に対応できなくなりました。その後短期間の受託や派遣での業務を続けながら、Microsoft Windows のプログラムをキャッチアップしていました。この約3年半は、私のエンジニア人生の中で暗黒時代と言えるかもしれません(笑)。
2000年代に入り、電気・電子楽器のメーカーでの新モデル開発で、初めて組み込み型ソフトの開発を経験しました。製品の発売日が決まっており、納期が非常に短いプロジェクトで残業が続きましたが、なんとか間に合わせることができました。
その次に、同じ会社で楽器同士を1本のネットワークケーブルでつなぐシステムの開発部署に回りました。さまざまな楽器の違いを吸収して、ユーザーインターフェースのソフトウェアにつなぐためのミドルウェアの開発を担当。ここでは、ベースとなるプログラムを1つつくり、パラメーターの変更で多数の楽器に対応できる構成とするなど、開発のシンプル化を図りました。そして、このときの開発ターゲットが、オブジェクト指向のプログラム言語だったため、過去に学んだ知識に大変助けられました。
この部署では、私のキャリアの中では最も長く、9年ほど継続することができました。それまでは単独で配属されることが多かったのですが、ここはメイテックのエンジニアもかなりいて、協力しながら仕事ができたことも安心感がありました。その後、別のプロジェクトも担当し、計15年お世話になりました。
上流開発を担うエンジニアへ。
若手の育成にもやりがい
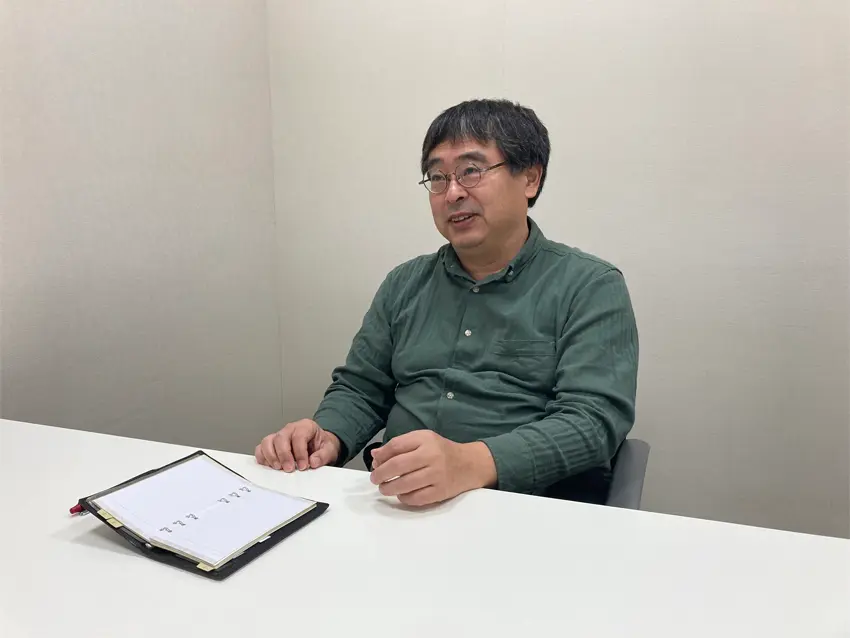
実は、このお客さまにいる時に、リーマンショックが起きました。多くのエンジニアが契約終了になりましたが、幸いにも私は契約を継続でき、残ることができたのはありがたかったです。
この契約の終了後は、いくつかの企業で働きました。工場の生産ラインを制御するシステム開発を担当した際は、ソフトウェア的なことだけでなく、生産ラインでのちょっとした作業を助ける治具をつくって、作業者から喜ばれることもありました。こういう治具は、精巧なものは必要ありませんから、不器用な私にはちょうど良かったんですよね(笑)。
次は、大きく変わってゴルフカートのシステムを開発しました。最初はゴルフ場がカートの居場所を管理するためのナビシステムをつくっていたのですが、カートの性能が不足していてうまくいきませんでした。その流れで、IoTを活用したゴルフカートの開発チームに2年ほど入りました。
60歳間近で契約終了した際は、私としてはもう次の仕事は見つからないかと思っていたのですが、幸い3カ月後に次の配属先が決まり、現在も働いています。ここではロボットアームを制御するシステムの上流開発をしています。自分でコードを書くことはなく、一緒に業務するメイテックの23新卒エンジニア3人をトレーニングする役割も与えられています。若い人とは、考えも価値観にもギャップはありますが、人を育てることは自分の成長にもつながり、やりがいを感じています。
FORTRAN から始まり、C、C#、C++やJAVAとその都度必要だったりトレンドだったりする言語を習得し、成果を出してきました。今では、無理なくどんな言語も習得できる自負があります。定年を迎えますが、お客さまから依頼があって、体が動く限りは仕事を続けていきたいと思っています。
(インタビュー:2024年1月13日)